<以下、転載部分>
「万葉集」に登場する植物を頻度順に並べて、「聖書」と比較すると、明瞭にその性格のちがいがみられる。(以下、比較表)
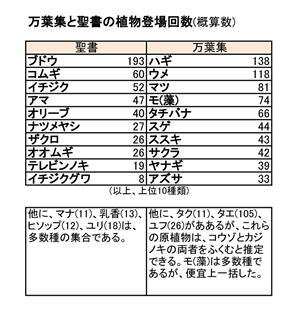
聖書では、上位10位までのうち、九つまでが実用植物であるが、万葉集では、上位10位までは全部実用植物でない。その中には「ウメ」が2位にあるが、これは花をうたっており、アズサは、弓材を意識しているが、それをとくに強調していない。万葉集の植物は当時の植物への美学的評価がその中心となって登場している。
このようなちがいは、聖書は宗教的散文であるが、万葉集は抒情詩集であるからだ、という説明は、一部しかあたっていないであろう。
詩集にしても「唐詩選」をめくってみると、そこに登場する植物の種類は貧弱で、草、花、藪、芳樹、百草、昔樹(昔の樹)といった概念的な取扱いの植物が多い。ところが万葉集では、ハギ、ウメ、マツ、サクラといったような植物名がズバリと登場するのがほとんどである。(中略)
奈良朝の頃の日本の上流社会には、植物を美学的に評価する文化が成立していたことは疑いない。とり上げられた植物を個々に吟味してみると、そこには、少数の栽培花卉、たとえばウメ、タチバナの他、モモ、アンズ、ハネズ(ベニバナ?)がある。これらは、いずれも中国から渡来して栽培されていたもので、当時の先進文明である中国文化の偲ばれるものであり、とくに「ウメ」はその意味で代表的であった。
しかし、万葉集の中でうたわれた植物の圧倒的多くは、日本原産植物である。
<転載、以上>
こうした比較の方法論は、確かにその文化の違いを理解するのに役立ちます。全体像の把握には効果的でしょう。ただ、ここで注意してほしいのは、中尾氏も一部、懸念を示している、この試みが西欧の「宗教的散文」という古典と日本の「詩集(歌謡)」という古典の比較という点です。西欧と比較して日本の花文化の特異性を語るためにこうした比較がなされているのはわかります。ただ、中尾氏も指摘してきたように、東洋花卉センターの発展は、中国から日本へと展開してきたという事実からも、日本の古典と中国の古典の比較がより、重要であるように思えます。
中尾氏も指摘しているように奈良朝は、中国文化を取り入れ、渡来文化が開花した時代でした。当然、この時代に成立した「万葉集」自体、中国文化の影響化に生まれています。
実際、中尾氏も取り上げている中国古典詩集の「詩経」は、中国文化の初期歌謡として、「万葉集」と比較されることが多い古典です。「詩経」と同様の文化的な背景に成立した歌謡としての「万葉集」を取り上げた貴重な最新の比較研究(白川静氏の「詩経」と万葉集の「初期歌謡」「後期歌謡」での研究実績)は、「万葉集」と「詩経」に登場する植物の比較をする際に是非とも知っておきたい研究です。
「詩経」は、前9世紀をその中心年代とし、「万葉集」は、8世紀前半を中心としています。その絶対年代は、千数百年を隔てているのですが、影響という側面もさることながら、その二つの古代歌謡が成立した背景の共通性は、この二つの古典を比較することの重要性を示しています。白川静氏は、「初期万葉論」の第一章の「比較文学の方法」で以下のように述べています。
<以下、「初期万葉論」より転載>
「詩経」は、風(ふう)と呼ばれる十五の地域にわたる民謡、小雅大雅と呼ばれる西周期貴族社会の儀礼詩、そして王室の廟歌である頌と、合わせて三百五篇より成る。我が国の「万葉集」もその歌集としての性格は「詩経」のそれに近い。それで比較文学的研究の対象としては同じく古代歌謡とよばれる各民族の古典の中でも、「詩経」が最も比較すべき共通の問題点をもつはずである。もとよりそれぞれの中心とする年代は、千数百年を隔てており、また「詩経」は、作者をもつことのない歌謡集であるが、「万葉集」にはすでに多くの作者があり、その家集すらあるという、かなり重要な相違がある。しかしそれにもかかわらず、この両者の間に比較文学的な研究が可能であるとするのは、そのような古代詞華集の成立する歴史的条件において共通するところがあり、また、その文学の性格において共通するものがあると考えられるからである。
<転載、以上>
「詩経」には、約135種の植物(木本植物61類・草本植物71種・蕨類植物2種・著生地衣類1種)が収録されいます。これらの植物の解説した文献は、江戸時代、明治と日本でも出版されたり、その登場する動植物の文化的な意味を研究した研究書も多く発行されています。
また、白川氏は、「万葉集」を取り上げる際に「前期(初期)」と「後期」に分けて万葉論を展開した意味を以下のように語っています。
<「初期万葉論」より転載>
前期(万葉集)は、巫祝的呪誦の文学をその本質としており、後期のそれ(万葉集)は士大夫の詠懐的文学であるということができよう。前期の作者として確かなものとしては、まず人麻呂をあげるべきであろうが、人麻呂は、古歌謡の伝統に立って、その呪的儀礼歌を宮廷文学として完成させた人であり、またその文学は、その死と共に終わっている。人麻呂は、その様式の完成者であり、また同時に最後の歌人であった。その文学が旅人、憶良、家持らの後期の文学と甚だしく異質なものであることはいうまでもないが、それはそのような文学を生んだ文学的基盤、または生活者としての時代意識の相違が、すでに異質なものであったことを示している。
<転載、以上>
このサイトでもこの白川氏の研究をひも解きながら、「万葉集」と「詩経」それぞれに登場する植物を調べていきたいと考えています。日本と中国で様々な花が歴史的にどのように取り上げられてきたかを調べる際に白川氏の「詩経」、「初期万葉論」「後期万葉論」をそれぞれの古典の文化的な成立や歌謡の作者たちの背景を知るために、是非とも参考にしたいと考えています。
中尾氏は、「花と木の文化史」では、奈良時代以降、平安、室町と日本の花の歴史を追いかけて、その花文化、園芸文化が発展していったようすを取り上げています。
この基礎課程では、この平安以降の花文化の変遷の詳細は省略します。、園芸文化がそれ以外の芸能や文学などの他の文化との影響化で発展していく時代については、応用課程で「各花の品種」や「他文化ジャンルにみる花文化」を取り上げる際に取り上げる予定です。
<この項、了>