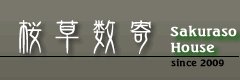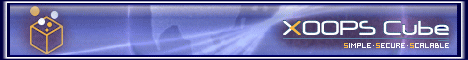「茶花」とは、茶室に生ける花のことをいいます。
どのように生けるかという話でよく説明に使われる文献として、千利休の口伝秘事を書き留めた「南方録」があげられます。その中の一文で後に利休七カ条、七則とされた文を以下にご紹介します。
茶は服のよきやうに点て、炭は湯の沸くやうに置き、花は野にあるやうに さて夏は涼しく冬暖かに、刻限は早めに、降らずとも雨の用意、相客に心せよ。
花は野にあるように
というフレーズがお茶における花を生ける極意とされています。
しかし、同じ南方録には、以下の花についての生け方についての一文もあります。
小座敷の花は、かならず一色を一枝か二枝、かろくいけたるがよし。勿論、花によりてふわふわといけたるもよけれど、本意は景気をのみ好む心いや也。四畳半にも成りては、花により二色もゆるすべしとぞ。
つまりは、自然にある花のままにということでなく、自然を感じさせるような生け方を説いており、茶室の姿、花入れと生ける花の調和を大事にということなのでしょう。
茶室や茶庭の設計に長年関わり、茶花の研究をされ、「淡斎茶花研究会」を主宰された加藤淡斎氏が茶花について語られている内容が私には、非常に茶花を表現する最適な言葉のように思え、以下にご紹介します。
<加藤淡斎・横井和子共著「茶花ハンドブック」より転載>
私にとって茶花との出会いは、茶会に招かれる身として京都・奈良の会に伺い、その中でふと席中の茶花への無頓着さを感じてしまったことにある。花の名前もお茶の先生によって異なっていたり、入れ方も決まりがあるわけではない。(中略)
茶花というものは、それぞれのお茶の流儀によって制約はあっても流儀はなく、利休の言うとおり「野山で咲いているように」これが趣旨である。しかし、野にあるがごとく、それで決まりがないから自然に入れるのでは、せっかくの花も花入も生かされない。互いのバランスを考え、互いに生かされてこそ茶花になるのである。亭主の思いが吹き込まれ、茶室という空間に融合された花は、花入という伴侶を得て、新たな命を客の前に披露してくれるのである。
<転載、以上>
花に無頓着ではなく、良く花を知り、茶会を催す人(亭主)の思いを花と花入の調和の中、茶室に表現する
ことが「茶花」だということなのでしょう。
どのように生けるかという話でよく説明に使われる文献として、千利休の口伝秘事を書き留めた「南方録」があげられます。その中の一文で後に利休七カ条、七則とされた文を以下にご紹介します。
茶は服のよきやうに点て、炭は湯の沸くやうに置き、花は野にあるやうに さて夏は涼しく冬暖かに、刻限は早めに、降らずとも雨の用意、相客に心せよ。
花は野にあるように
というフレーズがお茶における花を生ける極意とされています。
しかし、同じ南方録には、以下の花についての生け方についての一文もあります。
小座敷の花は、かならず一色を一枝か二枝、かろくいけたるがよし。勿論、花によりてふわふわといけたるもよけれど、本意は景気をのみ好む心いや也。四畳半にも成りては、花により二色もゆるすべしとぞ。
つまりは、自然にある花のままにということでなく、自然を感じさせるような生け方を説いており、茶室の姿、花入れと生ける花の調和を大事にということなのでしょう。
茶室や茶庭の設計に長年関わり、茶花の研究をされ、「淡斎茶花研究会」を主宰された加藤淡斎氏が茶花について語られている内容が私には、非常に茶花を表現する最適な言葉のように思え、以下にご紹介します。
<加藤淡斎・横井和子共著「茶花ハンドブック」より転載>
私にとって茶花との出会いは、茶会に招かれる身として京都・奈良の会に伺い、その中でふと席中の茶花への無頓着さを感じてしまったことにある。花の名前もお茶の先生によって異なっていたり、入れ方も決まりがあるわけではない。(中略)
茶花というものは、それぞれのお茶の流儀によって制約はあっても流儀はなく、利休の言うとおり「野山で咲いているように」これが趣旨である。しかし、野にあるがごとく、それで決まりがないから自然に入れるのでは、せっかくの花も花入も生かされない。互いのバランスを考え、互いに生かされてこそ茶花になるのである。亭主の思いが吹き込まれ、茶室という空間に融合された花は、花入という伴侶を得て、新たな命を客の前に披露してくれるのである。
<転載、以上>
花に無頓着ではなく、良く花を知り、茶会を催す人(亭主)の思いを花と花入の調和の中、茶室に表現する
ことが「茶花」だということなのでしょう。
投票数:98
平均点:2.96
|
茶事の花 |
風炉と炉<茶事の季節感> |